こんにちは、助産師のきいです。
前回の記事では、乳腺炎がどんな病気で、なぜ起こるのか、そしてどんな種類があるのかを詳しく解説しました。もしかしたら「私にも当てはまる症状がある…」「もしかして乳腺炎かも?」と思った方もいるかもしれません。
今回は、「乳腺炎かもしれない?」と思った時に自分でできる対処方法について説明していきます。すぐにクリニックや助産院へ駆け込みたくても、休日や夜中であったり、忙しくて行く時間が確保できない場合もあるでしょう。まずはこの記事に書かれているセルフケアを試してみてください。早期の対処が症状の悪化を防ぎ、回復を早める上で非常に重要です。
あなたの乳腺炎が早く良くなるよう、一緒に乗り越えていきましょう!
すでに症状が24〜48時間以上経過している、37.5℃以上の発熱がある、強い痛みがあるなどの症状がある場合、自分で判断できない、不安が強い、などの場合には無理せず早めに受診しましょう。
近くに助産院や産科クリニックはありますか?休日や夜間でも不安な場合には、大きな病院に相談してみてください。
1.授乳・搾乳の工夫 つまり解消と炎症軽減のために
乳腺炎の多くは、おっぱいの詰まり(乳汁うっ滞)が原因で起こります。そのため、乳汁をスムーズに排出することが、症状を和らげる上で何よりも大切です。
痛くない範囲で授乳を続ける (つまりを出すことが一番大切!)
痛みがあるからといって授乳をやめてしまうと、かえって乳汁が乳房に溜まり、症状が悪化する可能性があります。痛みが強くない範囲で、できるだけ頻繁に授乳を続けましょう。
【ポイント】
痛い側のおっぱいから先に授乳を始めることを試してみてください。 赤ちゃんがお腹が空いている時に、しっかりと吸ってくれることで詰まりが取れやすくなることがあります。もし赤ちゃんが嫌がったり、痛みが強すぎる場合は無理せず、状態の良い方から授乳しても構いません。

乳腺炎を起こしている方が痛くて、赤ちゃんに吸ってもらうのが辛い!

きいちゃん
そうですよね、乳腺炎になっているだけでとても痛いのに、授乳をするとさらに痛みを感じてしまうかもしれません。
乳腺炎でおっぱいが張っているときは特に、乳輪部分まで浮腫んでしまって、赤ちゃんが吸ってもうまく吸えない、痛みが強くて射乳反射(赤ちゃんが吸う刺激によって母乳が乳管から押し出される反射)が起きにくいということもあります。
まず最初に、しっかりと手のマッサージで乳輪と乳頭をほぐしてください。乳輪のむくみが取れると、指が柔らかく乳輪の中に入るようになります。マッサージしているうちにおっぱいも流れてくるようになり、赤ちゃんに飲んでもらったときの痛みが和らぎます。
二つ目に、先に反対側のおっぱいを少し飲んでもらう、ということです。「痛い方から先に」というのとは矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、ポイントは「少しだけ」ということです。少しだけ先に飲んでもらうことで、射乳反射が起き、痛い方のおっぱいを吸ってもらっても射乳反射が続き、効果的におっぱいを外に出せるようになるのです。
授乳姿勢の調整
詰まっている部分が赤ちゃんの顎の部分に当たるように、授乳姿勢を変えてみましょう。詰まっている部分からのおっぱいがよく出るようになります。
例えば、乳房の下側が詰まっている場合は、赤ちゃんがママの膝の上にまたがるように座る「縦抱き」を試してみるのも良いでしょう。乳房の外側が張っている場合には、フットボール抱きがおすすめです。
【ポイント】
赤ちゃんが乳輪まで深く吸着できているか、確認しましょう!
乳輪部分の深い地点に、おっぱいがでるポイントがあります。浅いと赤ちゃんが吸っていても、しっかりと出てくれません。また、乳頭へ負担をかけ、さらなるトラブルの原因になることもあります。乳輪が浮腫んでいて硬いことで浅くなってしまうこともありますので、マッサージでほぐすことも忘れずに。
授乳後の搾乳
授乳が終わっても胸の張りが軽減しない!ということもあるでしょう。また、乳腺炎になっているおっぱいの成分では、ナトリウム濃度が上昇し塩味が強くなります。これが原因で、赤ちゃんがいつもと違うおっぱいの味に気づいて、授乳を嫌がることもあります。
そんな時には搾乳も検討してみましょう。
特に授乳後に行う場合には、スッキリしすぎるほど搾乳してしまうと、おっぱいは「もっと母乳を作らないと!」とさらに多くの乳汁を作ってしまうため、制限するように言われることもありますが、適度に行えば乳汁を作り過ぎてしまうこともなく、乳房内組織への物理的な圧力を減らし、張りやむくみを和らげるケアにつながる場合があります。
【ポイント】
強すぎる搾乳はかえって炎症を悪化させたり、乳腺組織を傷つけたりする可能性があります。圧が調整できる搾乳器を使用し、1番弱い圧で射乳反射が出る程度にしましょう。
かける時間は〇〇分と一概には言えません。「少し軽くなったな〜」と感じたらやめるようにしてください。「スッキリした!」感じるまでとってしまうと、次回までにさらに多くのおっぱいが作られ、張りが強くなってしまう可能性があります。
よくある質問:赤ちゃんに害はないの?

乳腺炎になっている方のおっぱいで授乳しても、赤ちゃんに害はないの?細菌性乳腺炎の場合もあるって聞いたけど…

きいちゃん
乳腺炎が発生している状態で授乳を継続することについて、問題ないという研究結果が出ています(2)。
乳腺炎を起こしている方の赤ちゃんに原因となる菌が見つかった症例も少数ありますが、元々健康な方の皮膚にいる「常在菌」という菌の一種であり、お母さんと赤ちゃんのどちらから発生した菌なのか判別するのは難しく、母乳を継続するメリットと比較すると中止する必要はないと判断されているとのことです(2)。
2.冷やす?温める?使い分けがポイント!
乳腺炎の症状に応じて、冷やす・温めるを適切に使い分けることが大切です。誤った方法でケアすると、かえって症状を悪化させることもあるので注意しましょう。
基本は「冷やす」
乳房全体が熱を持っている、痛みがあるといった炎症症状がメインの場合は、患部を冷やすことで、痛みや熱感が和らぐと感じることがあります。
【冷やし方】
・授乳、搾乳の後、または授乳と授乳の間に冷やす(直前に冷やすと乳管が閉まって、おっぱいが出にくくなります)
・「気持ちいいな」と感じる場合に冷やし、不快だと感じる場合には実施しない
・水に濡らしたタオルを絞ったものを冷蔵庫に入れておき、冷やすときに取り出して使用する
・凍らせていない保冷剤を使用しても良いです
「温める」タイミング
体を温めることで乳管が広がり、乳汁が出やすくなります。また、温めることでリラックスできる方もいるでしょう。オキシトシンを分泌します。このオキシトシンは幸せホルモンと呼ばれ、リラックス効果があるだけではなく、射乳反射を引き起こします。
【温め方】
・温かいシャワーや風呂に浸かる
・温かいタオルを数分間おっぱいに当てる
・授乳の前に実施すると母乳の流れが良くなり、おっぱいが出やすくなります
・冷罨法と同様に、「気持ちいい」と感じる場合に、「気持ちいい」温度で、実施するようにしましょう
・乳腺炎になっているおっぱいの皮膚はダメージを受けやすくなっていますので、タオルを使用する場合には低温火傷に注意しましょう
おっぱいの冷罨法、温安法に特化した商品もあるようです。冷やしても凍らず、皮膚がデリケートな乳輪・乳頭には当たりにくい形をしています。
3.ママ自身の体調管理
乳腺炎は、ママの心身の疲れと密接に関わっています.しっかり休養をとり、体調を整えることが回復への近道です。
十分な休息と睡眠
乳腺炎の時は、体が「休んでほしい」とSOSを出している状態です。まずはご自身の体を休ませることを最優先に考えましょう。
パートナーやご家族、友人など、周りに協力を仰ぎ、積極的に体を休ませる時間を作ってください。赤ちゃんのお世話を代わってもらったり、家事を減らしたりするなど、積極的に助けを求められると良いでしょう。
自宅外でのフルタイムの仕事は、乳腺炎の頻度を増やすという研究もあります(4)。難しい方も多いと思いますが、可能であれば、病気欠勤を取れるといいですね。
また、休息を取る際には、赤ちゃんが頻繁に飲めるように、一緒に休息するのをお勧めします。

「赤ちゃんが頻繁に飲めるように、一緒に休む」って書いてあるけど、赤ちゃんが泣いていたらお世話をしたい気持ちは抑えられないし、ゆっくり休める気がしないよ

きいちゃん
こんなときこそ、ご家族の中で役割分担を明確にしていくのが大事です。
ママにしかできないこと以外は、ご家族にできるだけ引き受けてもらえるようにすると、ママがしっかりと休む時間を確保できます。例えば…
【ママができること】
・赤ちゃんが眠っているとき、泣いていないときには横で一緒に休む
・赤ちゃんのお腹が空いて泣いているときは、すぐに授乳する
【ご家族ができること】
・授乳以外の育児(おむつ交換、抱っこ、沐浴など)はできる限り全て
・お腹が空いていること以外が原因で泣いているときに、あやしたり抱っこする
・家事全般
もちろん、ご家族への負担が増えすぎてしまうのも心配です。どこまでだったらできるのか、仕事をセーブできるのか、誰がどの程度分担していくのかをしっかりと話し合っていけると良いですね。
場合によっては、家事代行業者や、産後ヘルパーなどを依頼をして負担を減らしていくことも一つの方法となります。
こまめな水分補給
いつも以上に意識して水を飲む事も重要です。水分摂取が少ないと身体が脱水になり、症状が悪化しやすくなります。さらに、母乳内の水分量が少なくなり、粘度が高くなることが予想され、乳管のつまりを悪化させる可能性があるのです。
成人は1日あたりに必要は飲水量は1,000ml〜1,500mlです(5)が、授乳期にはさらに多くの水分が必要となってきます。
例えば、生後一週間以降、赤ちゃんの体重が4.5Kgになるまでは、165ml/Kg1日に必要であるとされています(4)。つまり、現在の赤ちゃんの体重が4Kgの場合、1日あたり660mlもの母乳を赤ちゃんは飲みとっている計算になるのです。母乳の中で、水分は約87.6%であるため、少なくとも580ml程度の水分が普段よりも多く必要とされます。
1日あたり1,500〜2,000ml以上の水を飲むように意識してみるようにしてください。
【ポイント】
・一度に吸収できる水分量は200ml程度と言われており、一度に大量の水を飲んでも、ほとんどは尿として排出されてしまいます。ちょこちょこと、こまめに摂取するように意識しましょう。

ついつい水を飲むのを忘れちゃうの。気づいた時に飲むようにしているけど、1,500mlも飲めていなかった。どうしたらいい?

きいちゃん
1日の必要量って、意外と多く感じますよね。
私が病院でお母さんたちによくお伝えする方法は、「授乳の前後でコップ一杯ずつ飲みましょう!」という事です。
一杯あたり100mlとして、一回の授乳の前で一回、後で一回とすると、1日1,600mlは最低でも水を飲むことになります。(3時間おきの1日8回授乳として)
さらに、食事の際にコップ一杯ずつ飲むと、2,000mlを自然と飲めるようになるのです。
ぜひ試してみてくださいね!
判断が難しい場合には無理せず受診を!
ここまで乳腺炎のセルフケア方法について解説してきましたが、何よりも大切なのは「無理をしないこと」です。セルフケアを続けても症状が改善しない場合や、熱が下がらない、激しい痛みがある、赤く腫れている範囲が広がってきた、など、少しでも不安を感じたあら、すぐに医療機関を受診してください。早期に適切な治療を受けることで、ママの負担も軽くなります。決して1人で抱え込まず、プロの力を頼ってくださいね。
【参考文献】
1.Amir, L. H., & Academy of Breastfeeding Medicine Protocol Committee. (2014). ABM clinical protocol #4: Mastitis, revised March 2014. Breastfeeding Medicine, 9(5), 239-243.
2.日本助産師会 授乳支援委員会.乳腺炎ケアガイドライン2020. 第2版. 日本助産師会出版;2021.
3.水野克己,水野紀子.母乳育児支援講座. 第2版.東京:南山堂;2017.
4.NPO法人日本ラクテーション・コンサルタント協会編.母乳育児支援スタンダード.第2版.東京:医学書院;2018.
5.株式会社クイック. 1日に必要な水分量は、どのくらいなの?.看護roo!;2025. Available from:https://www.kango-roo.com/learning/2575/[Accessed2025 Aug 2].
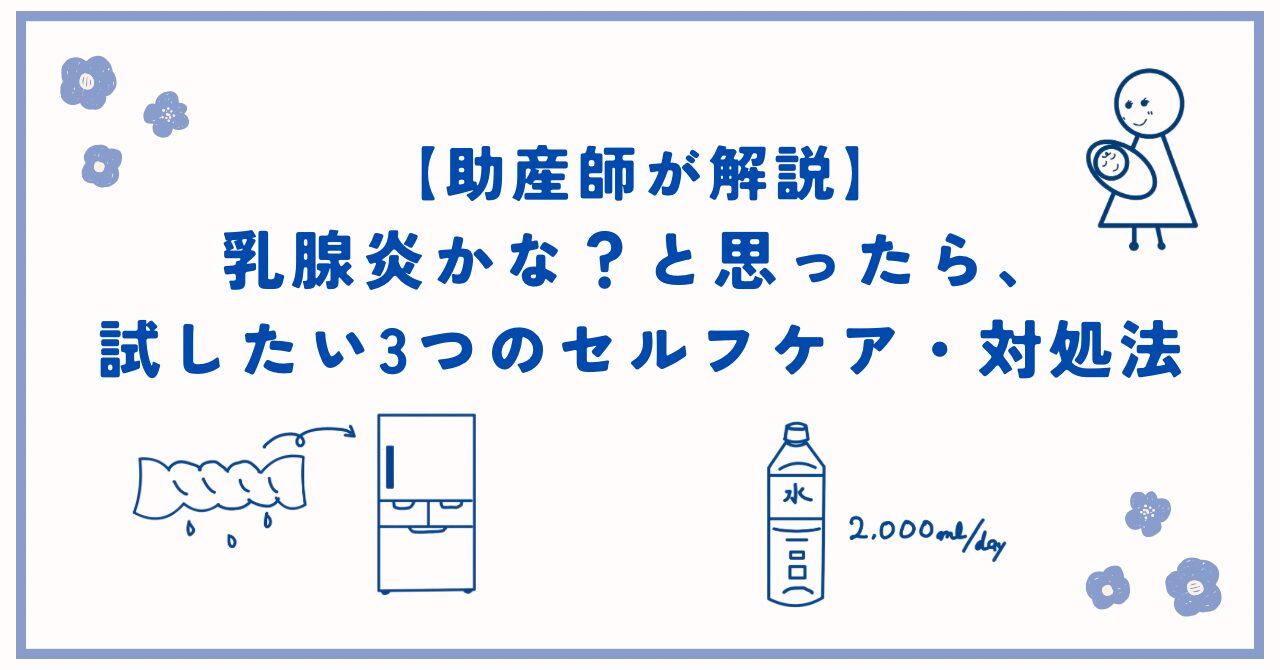
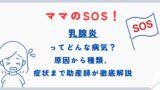
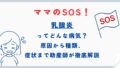
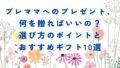
コメント