妊娠中の食事、「これで大丈夫かな?」と不安になっていませんか?
妊娠中は、おなかの赤ちゃんの健やかな成長のために、今まで以上に食事や栄養に気を遣いますよね。「何をどれくらい食べればいいの?」「食べてはいけないものは?」と、情報が多くて混乱してしまう方もいるでしょう。
タンパク質、鉄分、カルシウム、葉酸といった妊娠中に特に重要な栄養素の必要量と、効率的な摂り方、さらにはリステリア菌や水銀のリスクから赤ちゃんを守るために「控えてほしいもの」まで、分かりやすく解説します。
この記事を読んで、自信を持って妊娠中の食事を作って食べられるようになりましょう!
妊娠中に重要な栄養は?
赤ちゃんのためにもしっかり栄養を取りたい!そう思っても、どんな栄養をどれくらいの量取れば良いのかわからないですよね。
妊娠中に特に必要とされている栄養について解説していきます。1日あたりの必要量をg やmgで表示もしています。
食材の重さとその中に含まれる量は異なりますので、厳密に管理したい方は、食事管理のアプリなどを使用してみるのも良いでしょう。
タンパク質
タンパク質は、ママと赤ちゃんのからだを作るのに必要な栄養素です。
日本ではタンパク質の摂取が不足していると言われています。適切な量で、総エネルギー量の25%未満までの範囲でタンパク質を摂取した場合、死産と低出生体重児が減少したという研究があります。
【食材】
肉類、魚類、卵、乳製品、大豆や豆製品
【量】
毎食、片方の手のひらに乗る程度のタンパク質を含む食材
妊娠前体重が50Kgの妊婦さんの場合、妊娠初期33g、妊娠中期38g、妊娠後期58g必要とされています。(これは食材の中に含まれるタンパク質の量で、実際に食べる量はさらに多くなります)
鉄分
妊娠中には全身の血液が1.4倍になると言われています。その際に鉄分を含んだ成分が薄まってしまい、健康な方でも貧血になりやすくなるのです。貧血予防と赤ちゃんの血液づくりの材料や、疲れやすさの改善のために鉄分が重要になってきます。
動物性の食品に多く含まれるヘム鉄は吸収率が20〜30%と高いです。鉄分が多く含まれているとされる食材の中でも、動物性の食品を積極的に食べるのが良いでしょう。
【食材】
赤身のお肉(牛肉>豚肉の順で鉄分が多い)、ツナ缶、青魚(ブリ、イワシ、サバなど)、小松菜、ほうれん草、豆乳
【量】
妊娠初期10mg、中期・後期22.5mg
赤身のお肉100gで2.2mgですので、22.5mgもの摂取をするには「毎食鉄分の多い食材を使ってやっと足りる量」となるでしょう。間食で鉄分の多いものを取り入れることで、補うようにしましょう。

鉄分が多い食材を毎食食べなきゃいけないんですね。早いうちから習慣付けた方が良さそうです。

きいちゃん
少しでも吸収を良くするために、鉄分摂取のポイントをお伝えします!
①ビタミンCは鉄の吸収を促進します。切った時に中まで色がしっかりとついている野菜、ビタミンCの多い食材と一緒に摂取するのがおすすめです。
②緑茶や紅茶に含まれるタンニンは鉄分の吸収を抑制します。少しでも多く鉄分を吸収したい!という方は、食事の時には緑茶、紅茶などは避けるようにしましょう。
③レバーはダントツで鉄分の多い食材です。しかし、過剰に摂取することで赤ちゃんの奇形リスクが高まることも指摘されています。鉄分を摂取するためにレバーを日常的に摂取するのは避けましょう。
カルシウム
赤ちゃんのからだを構成するカルシウムの多くは、妊娠後期に吸収されます。
カルシウムは腸管から吸収されますが、妊娠後期には腸管からのカルシウム吸収が著しく増加します。過剰に吸収した分が尿の中に排出されるほどであり、妊娠する前と比べると必要量は増加しないとされています。
しかし、日本女性のカルシウム摂取量は必要量に満たないことも多く、いつも以上にしっかりと摂取する意識が大事になります。
【食材】
牛乳、ヨーグルト、スライスチーズ、豆腐、納豆、小松菜、水菜
【量】
650mg
牛乳3杯(1杯200ml)、ヨーグルト500g強、スライスチーズ7〜8枚、豆腐600g(豆腐2丁)
毎食に乳製品を多めに取り入れていくのが良さそうです。

きいちゃん
20代女性の平均カルシウム摂取量は384mgであるとのことです。いつもの食事に
・牛乳1.5杯
・ヨーグルト200g
・スライスチーズ3枚
・豆腐2丁
のいずれかを追加して食べるようにするのが良いでしょう。
葉酸
葉酸はビタミンB群に属する水溶性ビタミンで、不足すると貧血が生じることがあります。
妊娠する前後に葉酸をしっかり摂取していると、二分脊椎や無脳症などの神経管閉鎖障害の発症リスクを少なくすることができるといわれています(1)。
【食材】
ブロッコリー、ほうれん草などの緑黄色野菜、豆類、海藻類、果物、緑茶など
【量】
480μg
ブロッコリー(210μg/100g)、ほうれん草(210μg/100g)、焼き海苔(38μg/2g一枚)、納豆(120μg/100g)、ひよこ豆(110μg/100g)
妊娠中期以降の葉酸サプリメント摂取で小児喘息のリスクが上がったという報告があります(1)。
サプリメントによる過剰摂取には注意しましょう。

妊婦さんが特に気をつけたい食べ物
大きな魚
魚介類の中に蓄積された水銀も一緒に摂取してしまうことがあります。水銀がお腹の赤ちゃんへの影響があることが指摘されています。
お魚を全く食べてはいけない!というわけではなく、食べる魚の種類と量に気をつけて食べるようにしましょう。
特に、大きな魚は多くの魚介類を食べて成長しており、その過程でそれらの魚介類に含まれる水銀を多く摂取していると考えられるため、注意が必要になります。
お魚の種類と量に気をつけて
【注意が必要ない魚】
ツナ缶、カツオ、タイ、ブリ、鮭、サンマ、イワシ、アジ
これらの魚に含まれる水銀量は低いため、気にせずに摂取してもらっても大丈夫だといわれています。
摂取量に気をつけなければならないのは以下の魚です。
【一週間に160g以下までの魚】
キダイ、マカジキ、ミナミマグロ、クロムツ、イシイルカなど
【一週間に80g以下までの魚】
金目鯛、メカジキ、クロマグロ、メバチマグロ
水銀含有量が少ない魚を摂取するメリットは大きい

ブリやイワシは気をつけなくても良いって書いてあるけど、少しでも心配です。魚は食べたくないな…。

きいちゃん
水銀含有量が少ない魚は、むしろしっかりと摂取するようにしましょう。青魚(ブリ、イワシ、アジなど)に多く含まれるEPA・DHAといった成分は、赤ちゃんの脳の発達に重要です。
妊娠中にEPA・DHAを含む魚を摂取すると、生まれてくる赤ちゃんの神経発達に良い影響があると言われています。
実際に、2020年に発表された研究(9)では、魚由来のEPA・DHAを摂取することで、6ヶ月および1歳時点での発達の遅れを抑える可能性があるとの結果が出ています。
妊娠期だけでなく授乳期にも、これらの青魚を摂取することで、母乳に多く分泌されるようになります。
加熱しない生もの
リステリア菌は自然界に広く存在する細菌です。健康な大人であれば感染しても軽症で済むことがほとんどですが、妊婦さんの場合には特に注意が必要です。
リステリアの妊婦さんへのリスクとは?
妊婦さんが感染すると、胎盤を通じて赤ちゃんに感染が広がり、早産、新生児の髄膜脳炎・敗血症、胎児の死亡・死産を引き起こすことがあります。
リステリアの症状は?
リステリアに感染しても妊婦さんには症状がみられないこともありますが、発熱、筋肉痛や吐き気、下痢といった胃腸炎症状や、インフルエンザのような症状が見られることがあります。少しでも体調に異変を感じたら、すぐに産婦人科に相談しましょう。
リステリア菌が多いとされる「ハイリスク食品」
リステリア菌は低温の冷蔵庫内、塩分の高い環境でも増殖するという特徴があります。以下の食品はリステリア食中毒になりやすい食品ですので、避けましょう。
- ナチュラルチーズ(加熱殺菌していないもの)
- 肉や魚のパテ
- 生ハム
- スモークサーモン
などです。
「妊婦さんはお刺身やお寿司が食べられない」というのは、これらの料理が火を通さない生の状態で提供されることが多いからです。

チーズにはカルシウムも多く含まれているって聞いたけど、ナチュラルチーズは食べられないんですね。どのチーズを食べればいいの?

きいちゃん
食品の後ろの表示で「プロセスチーズ」と書いていあるチーズを選びましょう。プロセスチーズはナチュラルチーズを高温で一度溶かしたものをもう一度固めています。高温でリステリア菌や、その他の食中毒の原因となる菌は死滅しており、発酵もストップしているのが特徴です。
妊婦さんがリステリア菌を予防するためのポイント
リステリア菌は熱に弱いため、食品を十分に加熱することが最も効果的な予防方法になります。
肉や魚、野菜など、基本的に食べる直前に中心部まで火を通すようにしましょう。電子レンジで調理する場合には、内部までしっかりと温まっているかを確認しましょう。
生で食べる野菜や果物は、流水で時間をかけて丁寧に洗いましょう。カット野菜を使う際にも、念のため再度洗うとより安全です。
リステリアは低温でも増えます。冷蔵庫を過信せず、食品の期限を守り、開封後や調理後はできるだけ早く食べきるようにしてください。
栄養素が壊れにくい調理方法について
ここまで、妊娠中に食べた方が良いもの、避けるべきものについてお伝えしてきました。
栄養のあるものをしっかりと食べていても、調理過程で栄養素が失われてしまうことがあります。
効率良く栄養を取れるように、調理方法を工夫してみましょう!
加熱して野菜をモリモリ食べる
厚生労働省が推奨する1日の野菜摂取量は生の状態で350gです。日本人の平均摂取量は256g程度で、推奨量に届いていない現状があります。
妊娠中に必要な栄養は多く、野菜から多くの栄養を摂ることができます。いつもよりも野菜を多く摂取する必要があるのです。
野菜は加熱することで量が減り、たくさん食べることが出来ます。
加熱は電子レンジや蒸して、炒めて
茹でることで水溶性ビタミン(ビタミンCやB、葉酸など)が茹で汁に溶け出してしまいます。
一方で電子レンジで加熱した場合にはビタミンの喪失が少ないことが知られています。蒸した場合も同様です。
炒める場合には、栄養素の喪失はやや大きくなりますが、脂溶性ビタミン(ビタミンD、A、K、E)は炒める油のおかげで吸収率が高まります。
加熱調理をする場合には電子レンジ、蒸し料理、炒め物がおすすめです。茹でる場合には茹で汁まで摂取するのがおすすめです。
冷凍して料理の手間を減らして
妊娠中も働いているママも多いことでしょう。忙しい毎日の中でも栄養に気をつけて自炊するのは大変です。冷凍をした場合にもビタミンは比較的失われにくいです。
自炊ができずに必要な栄養素を取りにくい場合よりも、冷凍を活用してしっかり栄養をとったほうが摂取できるビタミンは多いでしょう。
健康的で栄養たっぷりの料理を一度にたくさん作って、冷凍保存して少しずつ食べる…といった方法が効率的です。
まとめ
妊娠中の食事について、助産師の視点から「食べてほしいもの」「控えてほしいもの」を詳しくお伝えしました。
妊娠中の食生活は、「完璧」を目指すよりも「継続」が大切です。不安や疑問は一人で抱え込まず、かかりつけの産婦人科や助産師に相談してくださいね。この記事が、妊婦さんの安心で健康な食生活をサポートする一助となれば嬉しいです。
【参考文献】
1.我部山キヨ子・武谷雄二.助産学講座6 助産診断・技術学Ⅱ[1]妊娠期第6版.東京:医学書院;2022.
2.公益財団法人長寿科学振興財団.ミネラル成分の鉄分の働きと1日の摂取量.長寿ネット;2025.Available from:https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyouso/mineral-tetsu.html[Accessed 2025.09.28].
3.一般社団法人日本スポーツ栄養協会.平成30年国民健康・栄養調査(1)栄養・食生活、身体活動等に関する状況.スポーツ栄養Web;2020. Available from:https://sndj-web.jp/news/000518.php?utm_source=perplexity[Accessed2025.9.29].
4.株式会社アイモバイル.葉酸が豊富な食べ物まとめ 摂取量の目安や効果的な摂り方も解説!.ふるさと納税DISCOVERY;2023. Available from:https://furunavi.jp/discovery/knowledge_food/202303-folicacid/?utm_source=perplexity[Accessed 2025.9.30].
5.平岡真実,坂本香織,坂戸市編.葉酸プロジェクトまるわかりBOOK.埼玉県:埼玉県坂戸市;2020.
6.厚生労働省.魚介類に含まれる水銀について.政策について;2010.Available from:https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/suigin/[Accessed 2025.9.30].
7.JAグループ.妊娠したら気をつけよう①摂取量に注意したい食べ物.JAグループ耕そう、大地と地域のみらい; Available from:https://life.ja-group.jp/food/premama/note05[Accessed 2025.10.2].
8.エコチル調査富山ユニットセンター.妊娠中のお母さんの魚摂取と生まれた子の発達の関係.エコチルとやま;2020. Available from:http://www.med.u-toyama.ac.jp/eco-tuc/result/sakana2.html [Accessed2025.10.2].
9.Kei Hamazaki,Kenta Matsumura, Akiko Tsuchida, Haruka Kasamatsu,Tomomi Tanaka,Mika Ito,Hidekuni Inadera.Maternal dietary intake of fish and PUFAs and child neurodevelopment at 6 months and 1 year of age: a nationwide birth cohort—the Japan Environment and Children’s Study (JECS).The American Journal of Clinical Nutrition.2020;112(5):1295-1303.
10.厚生労働省.リステリアによる食中毒.厚生労働省;Available from:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055260.html [Accessed2025.10.5].
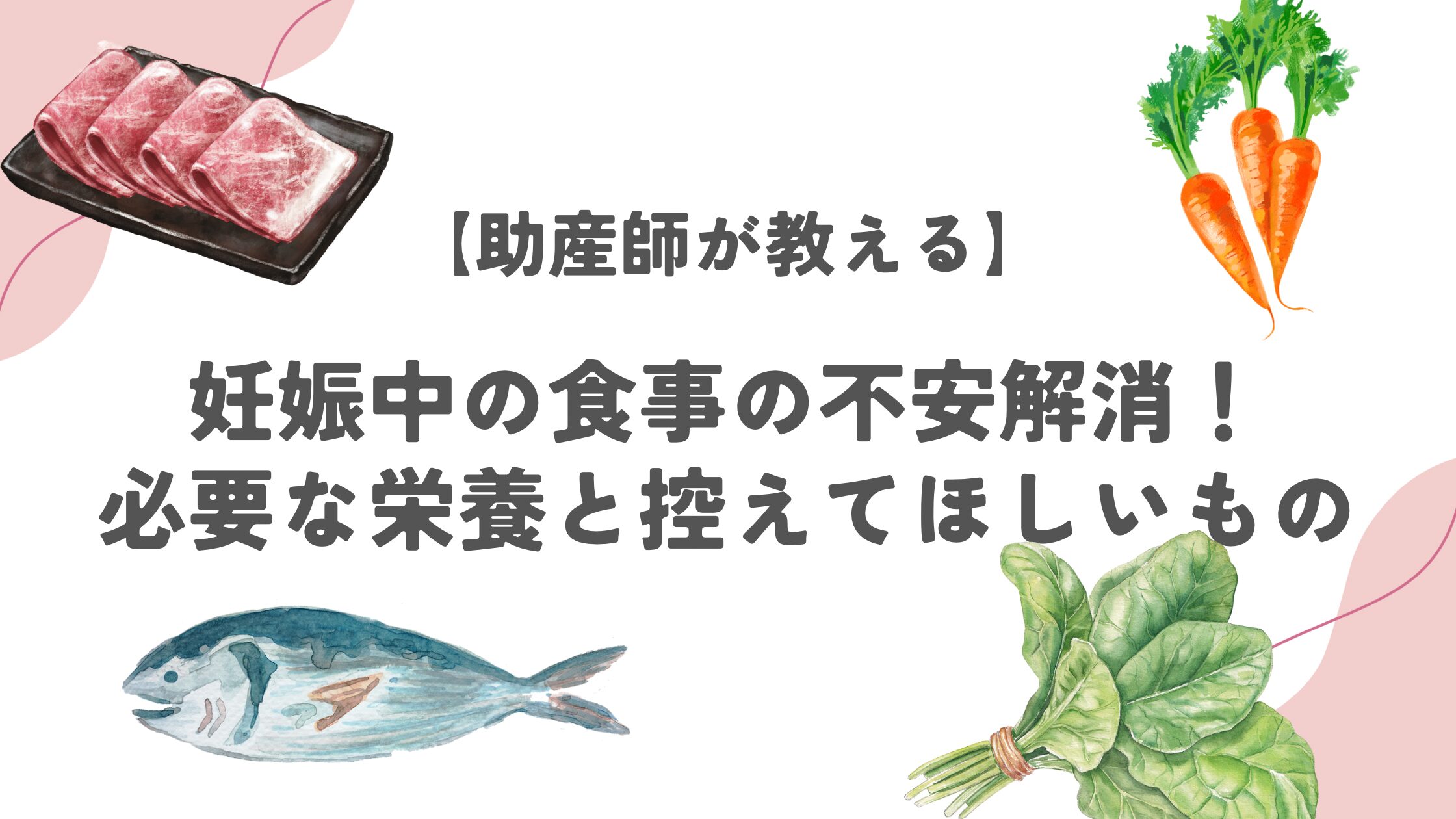
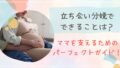

コメント